
山あいの集落でトマトを育て農業を営む落合桂。彼と共に暮らしている鈴木智は東京で政治活動をしていた。
彼女は都会での生活を捨て故郷に帰り、この地で桂と生活している。
桂はかつて酒で失敗をした経験を持つ。二年ほど酒を断っている彼だが、自宅の納屋で秘かにどぶろくをつくっている。
ある日、智はそのどぶろくを見つけてしまう。何も言わない桂に、自分の思いを伝えようとする智だが、桂の言葉からは彼の思いが見えてこない。
一方、桂は都会で暮してきた智に対し、この土地で一緒に暮していってよいのか小さな不安を抱いていた。
見えなくなる互いの思いと、相手への想いがぶつかったとき、智は彼女のやり方で桂の思いに問いかけた。
都市から遠く離れた山村に暮らすふたりのできごと。

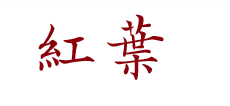
青春の一途さと煩悶である。父の故郷・岡山県湯原に定住、トマト農民としての自立にひたむきな日常を被写体に、自ら脚本、監督。
「牛飼(うしかひ)が歌よむ時に世のなかの新しき歌大いにおこる」と昂然だった歌人・伊藤左千夫のように、トマト作りが映画を撮るとき、世の中の新しき映画はさらにうねるのである。
河瀬直美が奈良を離れぬように、山崎樹一郎も山合いの村を凝視し、発想し、動かない。足元を掘る。そこに泉の湧くことを河瀬同様、若き山崎も知っているのだ。
見えない明日を見ようと努める青春、添えな男女が添える日の準備の準備を約束させる結末まで、流れでなく、ショットを重ね、つなぐ、反ドラマ的ドラマで農村と都会を結びつけたのである。
一極集中の東京へではない。農村へ帰ろう。土と山の中に、都市文明が奪った人間的絆を 再生させる可能性がある。若き監督はそう考えている筈だ。
木津川 計 (「上方芸能」誌発行人)
山崎樹一郎さんが、トマト農家に転身されると聞いて数年。作品には、瑞々しく熟すトマトが、すさんでいく若者の姿と対比して描かれる。おそらく都会で社会変革の夢破れ、農村に 戻った若い女。 人間的なつながり、土に生きる喜びを期待して戻った筈であるが、希望を見出すにはほど遠い山村の現実。・・・(中略)・・・現代の農村問題を深刻にえぐりながらも、 直載的な切り込みをしない監督の美意識があちこちに見られ、山々はあくまでも青く、せせらぎの音が耳に残る。
多くの方々にご覧頂き、この国の農に生きる若者の静かな怒りと紡ぎ始めた希望を感じとってほしい。
広川律子(大阪千代田短期大学教授)
映画がただ映画に向けてつくられ、人間も感情も言葉も風景も、映画を構成する“装置”に成り下がりつつある今、『紅葉』はこの世の音をすべてかき消し、山を通過する一瞬のわずかな音に、耳を澄ますことか ら始まる。
山の音がこの映画にコダマしている、とまでは言えない。
ただ私たちに、只事ではないその背を向ける男が、その視線の先に見据える柿の木、
静まり返った夜明けの道で、女が踏み殺してしまうケモノの心臓、
私たちは今、映画でそれを見つめ、聴くことをもう一度大事とすべきだ。
― 『紅葉』は、ゼロ年代・ゼロ世代などと呼ばれた最初の10 年がいま終わる、前夜にこそ、撮られた映画だと思う。
木村 文洋 (映画監督『へばの』)